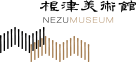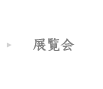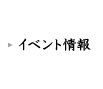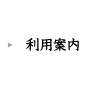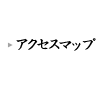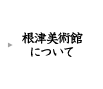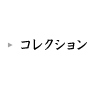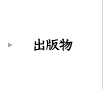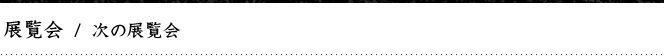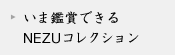在原業平生誕1200年記念 特別展
在原業平生誕1200年記念 特別展
伊勢物語
美術が映す王朝の恋とうた- 2025年11月1日[土]~12月7日[日]

| 休館日 | 毎週月曜日 ただし11月3日(月・祝)、11月24日(月・祝)は開館、翌火曜休館 |
|---|---|
| 開館時間 | 午前10時~午後5時(入館は閉館30分前まで) |
| 入場料 |
オンライン日時指定予約 一般1500円 学生1200円 *障害者手帳提示者および同伴者は200円引き、中学生以下は無料 |
| 会場 | 根津美術館 展示室1・2・5 |
平安時代前期に活躍した在原業平(825〜880)は、天皇の孫で、和歌に優れた貴公子です。『古今和歌集』などに収められる業平の和歌からは、恋多き生き方も浮かび上がってきます。そうした業平の和歌を中心とする短編物語集が『伊勢物語』です。『古今和歌集』が成立する延喜5年(905)より少し前から10世紀後半にかけて徐々に章段を増し、やがて125段からなる形が定着しました。
続く11世紀初頭に書かれた『源氏物語』の「絵合」巻には、絵の優劣を競う遊びのなかで伊勢物語絵巻が登場し、物語がすでに絵に描かれていたことをうかがわせます。以降、『伊勢物語』は、『源氏物語』と並び、日本の文化・芸術のあらゆる分野に多大な影響を与えることになります。
2025年は業平の生誕1200年にあたります。それを記念して『伊勢物語』が生み出した書、絵画、工芸を一堂に集める展覧会を開催します。『伊勢物語』の核心をなす和歌に焦点をあわせ、それを味わいながら、また『伊勢物語』の造形化における和歌の働きに注目しながら、ご覧いただきます。

- 在原業平像
- 室町時代 16世紀
根津美術館蔵 -
在原業平は六歌仙のひとりに数えられる歌詠みとして名高い。画像は束帯を着して上畳に坐し、右手に筆を、左手に紙を持って和歌を案じる姿に描かれる。同図様の業平像として南北朝時代の先行作(個人蔵)があるが、それに次ぐ年代の遺品として貴重。
初公開


- 伊勢物語絵巻(部分)
- 鎌倉時代 13世紀
和泉市久保惣記念美術館蔵 -
『伊勢物語』を題材とした現存最古の彩色絵巻。第23段「立田越え」は、新しい女のもとへ通う夫を妻は快く送り出し、道中の無事を祈る歌を詠んだので、その歌に感じ入った夫は女を訪ねることをやめたという話。夫を気遣う妻と、出かけたふりをして邸内をうかがう夫を描く。
前期【11/1(土)~12/16(日)】のみ展示

- 伊勢物語図 行く水に数かく 土佐光起
- 江戸時代 17世紀
個人蔵 - 第50段、互いの浮気心をめぐり女が詠んだ「行く水に数書くよりも」からはじまる和歌の情景を描く。非現実の歌の世界を表す画中にさらに男の返歌が書され、表現は重層化する。土佐光起(1617~91)による典雅な大和絵作品。

- 八橋蒔絵硯箱
- 江戸時代 17世紀
サントリー美術館蔵 - 「八橋」の場面の和歌は、「かきつばた」の5文字を五七五七七の各句の初めに据えて詠まれた。この硯箱の意匠は、歌を導き出すモチーフだけで物語の情7趣、さらに歌そのものをも想起させる。工芸における人物を排した「留守模様」は「歌絵」と関係が深い。